
と の こ お り
都於郡城
二ノ丸虎口


| 所在地 | 宮崎県西都市鹿野田 |
| 形式 | 平山城 |
| 主な城主 | 伊東氏 |
| 遺構 | 曲輪・空堀・土塁 |
| 指定・選定 | 国指定史跡 |
| 訪城年月日 | 2025年3月21日 |
| 満足度 | A B C D E |
| 登城難易度 | A B C D E |
| 車での登城 | 不可 |

本丸東虎口に建つ「都於郡城本丸跡」の碑
三ノ丸
二ノ丸跡
駐車場から本丸跡へ
奥ノ城


奥ノ城の説明版
奥ノ城の虎口

本丸と奥ノ城の間の堀切
本丸と奥ノ城の間の堀切


無名曲輪
西ノ城の南側にある無名曲輪


西ノ城から見た三ノ丸
西ノ城


西ノ城説明版(拡大可)
西ノ城虎口

三ノ丸から見た西ノ城
三ノ丸からの眺望


三ノ丸跡

三ノ丸跡

三ノ丸
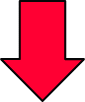
三ノ丸説明版(拡大可)

二ノ丸(右)と三ノ丸(左)の間の空堀


二ノ丸から見た三ノ丸・西ノ城
三ノ丸
西ノ城


二ノ丸(右)と三ノ丸(左)の間の空堀





本丸(右)と二ノ丸(左)間の巨大空堀


本丸跡(南部分)


本丸から二ノ丸を望む
本丸(左)と二ノ丸(右)間の巨大空堀
本丸土塁
本丸跡(北部分)


本丸庭園跡

本丸跡


本丸東虎口


本丸東虎口


本丸東虎口


駐車場に設置された伊東氏四十八城の分布図(拡大可)
駐車場北側にある中馬場跡
工藤左衛門尉祐経は建久元年(1190年)正月、鎌倉幕府から日向国の地頭職に補せられました。その嫡男である伊東祐時から6代目の
祐持は足利尊氏に従って勲功を認められ、建武2年(1335年)都於郡300町を賜り、その一族を連れて関東の伊豆から都於郡に下向して
来ました。都於郡伊東氏としては、祐持が初代の城主ということになります。その後2代目伊東祐重が山城としての都於郡城の築城工事を
行いました。築城の模様については、「日向記」(天正18年・1590年)に詳細に記録されています。築城に際しては本丸に存在していた伝説・
高屋山上陵(祭神 彦火々出見尊)を掘り、出土品は城の近くにあった一乗院に移したと伝えられています。
都於郡城の主体部としては、本丸、二ノ丸、三ノ丸、西ノ城、それに奥ノ城の5つの曲輪(くるわ)があります。この内城としての五城郭は、
一名「浮舟城」とも称されていました。この五城郭に対しては外城としての南ノ城、中尾城、東ノ城、日隠城などが内城をとりまくように築城されて
います。また、各曲輪の縁辺部には土塁が構築され、曲輪と曲輪との間には空堀もつくられて、外敵防御体制をとるようになっています。
南北朝以来約240年間、この都於郡城を本城として日向一円を掌握した伊東氏も、10代目伊東三位入道義祐の時代、天正5年(1577年)
12月、都於郡城落城とともに一族を連れて豊後に落ちのびて行くことになり、伊東氏の栄華は終わりをつげることになります。
<現地案内板より>
都於郡城
奥ノ城の土塁
二ノ丸から見た三ノ丸
二ノ丸土塁
二ノ丸跡
本丸跡(南部分)


本丸跡に建つ伊東マンショの像
~マンショの母は日向伊東氏10代当主義祐の娘であり、
マンショはここ都於郡城で生まれた~
本丸跡
三ノ丸虎口
二ノ丸説明版(拡大可)
本丸西虎口
本丸東虎口